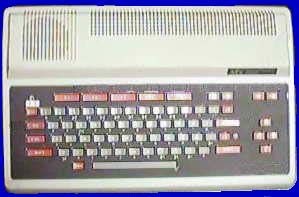
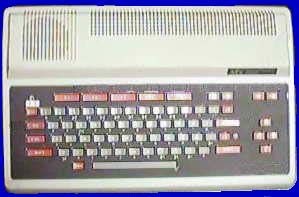
考えてみると、この頃のコンピュータはCPUの差はあまりない。今のペンティアムなどのようにクロック数の違いもなかった。高いパソコン(この頃はまだマイコンという言葉の方が主流だったように思う。パーコンなんて言い方もあった)も安いパソコンも同じCPUで、それ以外の性能で競っていた。
そのために、今のパソコンを見ると、「なんだ、たかがCPUが違うだけで面白みはないじゃないか」と思ってしまうのかもしれない。単に私が、根が色物好きだということかもしれないが。
メモリの進歩は目覚ましいもので、当時はまさかメガバイト単位の時代が来るとは想像もできなかった。なにしろ、千倍だもの。今の人は、あの頃はわずか1KBしか標準実装されていたマシンもあったなんて、想像もつかないだろう。原稿用紙2枚分が記録できないんだから。
このPC6001では、オプションでROMもRAMも32KBまで拡張できた。ただROMは、ゲームやアプリケーションのプログラムを収めたカセットを差し込んで電源を入れるだけで使えるという、ゲーム機のような使い方を想定していたようだ。なかなか斬新なアイデアである。しかし、残念ながらソフトは数えるほどしか発売されていない。
もっとも活躍したROMカートリッジはおそらく拡張ベージックカートリッジだと思うが、なにしろ、カートリッジを差し込む場所は一つしかなく、RAMもカートリッジで拡張だったので、そのままでは併用できなかった。(拡張ユニットの購入で併用は可能となったが)
他のコンピュータが80×20の表示ができたので、この表示能力は弱いといわれても仕方がない。しかし、PC6001はTVに繋ぐことを前提にしていたので、これ以上の文字は見にくいと判断されたのだろう。
しかし、実はPC6001の文字の最大の特徴は別にある。まず、ひらがな表示ができたことだ。他のコンピュータでの罫線用などの記号のかわりに採用されたものだが、これが実にフレンドリーな印象を与えた。同時におもちゃっぽいイメージも与えたが。しかし、他のコンピュータで使用できる記号が使えないデメリットもあり、後のシリーズでは切り替え式で表示できるなどの措置がとられた。意外とユーザーの要望に応えていたシリーズだといえるのではないだろうか。
他にもテキスト画面を2枚持つことができたという特徴もあった。
PC8001とは異なり、ドットごとに色を付けられた。とはいうものの、最大解像度では2色しか出せず、128×192でも4色、64×48というあまりに荒い解像度でしか最大色の9色は出せなかった。
したがって、もっとも実用となったのは128×192の4色グラフィックモードだったのではないだろうか。
ただ、その後アスキーのゲームパックでは、256×192のモードで、TVの色ずれを利用した4色表現や、隠されたグラフィックモード128×96モードなども使われた。
最大グラフィック画面を3枚使用できたのも特徴。この機能を使って、裏画面でグラフィックの書き換えをしてちらつきを防ぐ技は、常識のように使われていた。グラフィックの書き換えに時間がかかるからこその裏技で、グラフィックを書くためにアクセラレータを載せているような今のコンピュータでは、必然性のないものだろうが。
断っておくが、FM音源ではない。もちろんPCM音源などではあるわけもない。
PSG音源、いかにもコンピュータっぽいピコピコした音である。しかし、この音源は効果音作りにはなかなか向いていて、ゲームには合っていた。
また、他のパソコンがブザー音しか鳴らせなかったり、鳴らせても単音で大したオクターブ数はなかった時代である。これだけでも驚くほど斬新だったのである。
家庭用のTVであれば、たとえビデオ入力がついていないものでも接続できた。逆に言うと、一般のコンピュータが使うRGBモニターには接続できなかった。良くも悪くもゲーム機なみ。
そのままゲーム画面をビデオに落とせていいな、と思った人へ? その通りではあるが、当時はまだビデオが高くて一般で持っている人は限られていた。
別に珍しいことではない。当時のパソコンはカセットテープを標準的な外部記憶装置として使っていたのだ。フロッピーディスクは高嶺の花だったのだ。今じゃ考えられないけどね。ちなみにハードディスクなんて、当時はパソコン用にはどこにもなかったと思う。
ちなみにこのPC6001用として発売されたカセットレコーダはなかなか性能が良く、他のシリーズや他のメーカーのパソコンユーザーにも使われていた。
要するにジョイスティックインターフェイス。アタリ方式といわれる9ピンコネクタで、ここに接続するジョイスティックのおかげで、貧弱なキャラメル型と呼ばれたキーボードをあまり痛めずに済んだ。
特筆すべきは、このインターフェイスに接続できるデジタイザ(タッチパネル)が発売されたこと。抵抗シートを2枚重ねて、押された部分を読みとる簡単なものだったが、PC6001のグラフィックには十分な性能を持っていた。
ROMカートリッジなどを挿す場所である。普通、外部バスというと将来のための機能拡張のため、なんて書いてあるマシンが多くて、そのくせ何にも使えないままに終わってしまったなんてのもあったが、PC6001では、最初から頻繁に使われたわけだから、考えようによってはすごい。
ちなみにPC6001のマニュアルには、ここにミニフロッピーディスクユニットも接続できると書いてあるが、不可能である。本体内蔵のBASICは、それをサポートもしていないのだから。ここにオプションの拡張ユニットを挿すことによって、バスを4つに増やし(カートリッジ用は3つ)、それによりようやくフロッピーもめでたく使えるようにはなったが。
いうまでもなく、プリンタインターフェイスは装備されていた。安価なプロッタプリンタなども発売された。なお、RS-232Cインターフェイスはオプションとなっていたが、まだパソコン通信という言葉もなかったような時代。はたして、PC6001でこれを使った人はいたのだろうか、私には疑問である。
| PCS-6001R N60拡張ベーシックカートリッジ
|
| PC-6006 ROM/RAMカートリッジ
|
| PC-6011 拡張ユニット
|
| PC-6021 サーマルプリンタ
|
| PC-6022 4色カラープロッタプリンタ
|
| PC-6031 ミニフロッピーディスクユニット
|
| PC-6041 グリーンディスプレイ
|
| PC-6042 カラーディスプレイ
|
| PC-6051 タッチパネル
|
| PC-6052 ジョイスティック
|
| PC-6053 ボイスシンセサイザー
|
| PC-6081 データレコーダ
|
| PC-6082 データレコーダ
|
