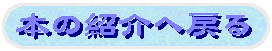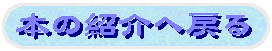
|
電話のベルが鳴っていた。 私は受話器を取り、耳にあてた。ザワザワとノイズが聞こえる。それに混じって、かすかに人の声がする。聞き覚えのある声だ。 しかしそれはだんだんと小さくなり、消えた。耳障りなノイズとともに‥‥。 受話器の向こうはそのまま沈黙してしまった。まるで電話の線が切れてしまったように全く音がしない。 おかしいな。 そう思いつつ、受話器を耳から離した。が、その瞬間はっきりと耳にはずんだ息と声が聞こえてきた。 「もしもし」 女の子の声だ。それも六つか七つくらい。 「聞こえますか?」 クスッと笑い声。 「ええ、どなたですか?」 私はすぐに間違い電話だと思ったが、相手が小さな女の子だったので、ガチャンとそのまま切ってしまうことはできなかった。 女の子は私の問いは聞いていないようだった。 「わたしね、今ひとりで電話をかけているの。ひとりでよ」 女の子は自慢するようにいう。 「パパもママも電話をおもちゃにしてはいけませんっていうの。でも違うの。わたし、おもちゃにしているんじゃないのよ」 私は黙って聞いていた。何といったらいいのかわからなかったというのが本当のところだ。なにしろ、これは『間違い電話』ではなく、この女の子の『おもちゃ』なのだから。 しかしただそれだけなら、私はこの少女に二言三言いって電話を切ってしまったことだろう。だが二日前、私は病弱だった娘を亡くしたばかりだった。しかもその年齢がこの電話の向こうの少女と同じくらいなのだ。 「わたし、お友だちが欲しかったの。パパもママもいつもわたしのとこにいてくれないから。とてもさびしかったの。だから電話をかけているのよ。わたし、いけない子?」 「いや」 突然問われて私はとっさにそう答えてしまった。 「よかった。もしいけない子だっていわれたら、わたし、今日一日ふくれっつらしてなくちゃいけなかったわ、きっと。ねえ、わたしのお友だちになってくれるでしょう? ミチのお友だちに‥‥」 私はギクリとした。ミチ 美知子は私の娘と同じ名である。 一瞬のうちに、私は娘の死んだ前日のことを思い出していた。 あの日、娘はとても明るい顔でベッドの上にちょこんと座っていた。それを見た私は娘をベッドに寝かせ、それから、何かうれしいことでもあったのかい、と聞いてみたのである。 「パパ、今日ね、ミチにお友だちができたの。ほんとうよ、ほんとうなのよ」 娘はとても興奮していた。 「そうかい。それはよかったね。でもちゃんと寝てなくちゃ。そんなにはしゃぐと、また胸が苦しくなるよ」 「ううん、大丈夫。それより聞いて。そのお友だちね、わたしのこと、ミチって呼んでくれたのよ。パパみたいに」 「ほう。それで、そのお友だちは男の子かい? それとも女の子かな?」 私は笑って、首を振った。 「ちがうわ。男の人よ」 「男の人?」 「そうよ。パパくらいだと思うわ」 「おやおや、おまえは知らない男の人とお友だちになったのかい? それで、その男の人はハンサムだったかい? パパのように」 「わからないわ」 娘は首をすくめ、白い歯をのぞかせた。印象的だった。ずっと寝たきりで頬は痩せこけ、目の縁はすこしくぼんでいた。唇はカサカサに枯れて、顔色もよくなかっただけになおさらだった。 「だって、わたしその男の人と会ってないもの」 「会ってない? そうか、また電話で遊んだんだな」 「うん。でもわたし、悪い子じゃないわ。その男の人、そういってくれたもの」 「あきれた子だ」 私は布団をきちんと肩まで掛けてやった。 「もうそんなイタズラしちゃだめだよ。ひとの迷惑になるからね」 「でも、わたし‥‥」 「もういいから、眠りなさい。なにも考えないで。パパがこうしてついていてあげるから」 そういうと娘はこっくりとうなずき、おとなしく目をつぶった。 だが、私はその後すぐに仕事の都合で娘のそばを離れなければならなくなった。そうして一夜明けて戻ってきたときには、もう娘の両の目はかたく閉じられていたのである。 「どうしたの? お友だちになってくれないの?」 受話器の向こうから心配そうな声が聞こえてくる。 「ミチ」 私はつぶやくようにいった。目の縁が熱くなる。 「友だちだよ。ずっと、ずっとパパはミチの友だちだよ」 その時、受話器の向こうの息づかいが急に遠くなり始めた。 「ずっと一緒にいるよ。だから‥‥だから、ミチ!」 頬を涙が伝うのを感じた。言葉が引っ掛かって続かない。 もうほとんど少女の声は聞こえなかった。 私はもう一度少女の声を取り戻そうと、やみくもに電話をたたいたり、ダイヤルを回したりした。 「ミチ、だから‥‥だから!」 私は受話器をしっかりと握ったまま、その場に崩れるように座りこんだ。涙を流しながら、声の出なくなった口を必死で動かし続けた。 受話器の向こうからは、ツーッ、ツーッと断続音だけが際限なく続いていた。
(了)
|