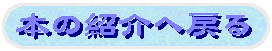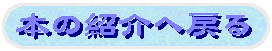幼い頃、私は祖父の家へよく行きたがった。
当時、両親の家が平屋だったせいもあって、古めかしい木造二階建の家が珍しかったというのも理由の一つである。私は祖父の家へ行くと、当時の私の身長ほどの幅しかない階段でよく遊んでいた。座り込んで階上を見上げると、傾斜が切り立った崖のように見えて、二階が自分の知らない別の世界のように感じたりしたものだった。
二階へと上がると畳敷きの広い部屋がある。一番奥には床の間。側面には漆喰の壁と障子戸があり、それを開けると部屋に沿った廊下が延びていた。この二階は別段何があるわけでもないのだが、私や私と同い年くらいの従兄弟たちにとってはいつも格好の遊び場だった。取っ組み合いをしたり部屋中を走り回ったりして子供の時間を費やしたものだった。
しかし、私が祖父の家に行きたがったのには別に理由がある。
ある日のこと、私はいつものように両親に連れられて祖父の家へとやってきた。しかし折悪く、隣に住んでいていつも一緒に遊ぶ従兄弟は、家族で旅行へ出掛けてしまっていた。私は両親が迎えに来る夕方まで一人で遊んでいなければならなかった。
私はいつものように階段でおはじきを飛ばしたりビー玉を転がしたりして遊んでいた。が、すぐに飽きてしまい、二階へ上がって何か面白いものはないだろうかと部屋の中を歩き回っていた。
何気なく床の間に飾られた壷に手を伸ばし、私はその下に古い鍵が置かれているのを発見した。どこの鍵だろう? 私は鍵をくるくると回しながらしばし考えた。
二階にはその広い部屋の他にもう一つ客間があった。それは廊下に面した引き戸の一つに通じている。廊下にはほかにもいくつかの引き戸と開き戸が面していた。しかしそのほとんどは押し入れで、客間への引き戸と同様に鍵など掛かってはいない。ただ一つだけ、鍵が掛けられて開けることのできない開き戸がその廊下の端にあった。
初めてその戸を見つけたとき、私は祖父に中に入りたいといった。しかし祖父は首を横に振りながらこういったのだった。
「この戸の鍵はね、おじいちゃんも持っていないんだよ。ずっと前になくしてしまってね」
もしかしたらその開き戸の鍵かも。私は鍵を握り締めるとその開き戸へと足音を忍ばせるようにして歩いていった。少し震える手で鍵穴に鍵を差し込む。鍵はすんなりと滑り込んだ。ドキドキしながら鍵を回すと鍵穴の奥でガチャッと鈍い音がした。
開いた!
そっと鍵を抜きだし、開き戸の取っ手を掴んでゆっくりと引く。
蝶番の軋みが不快な音を立てて開くと、私の前には一つの部屋が広がっていた。
そこはまるで物置のようだった。通風口らしいところから外の明りが差し込んでいたが窓は一つもなく部屋の中は薄暗い。天井には古びたシャンデリアが飾られていたが、電球は外されているようだった。部屋の中央には木製の大きな机と椅子。机の上には本がいくつも山積みされており、椅子には灰色のクッションが置かれていた。壁には絵や彫刻や陶器の並んだ棚が長く延びていて、いろいろなものが所狭しと置かれている。
私は、ゆっくりと部屋の中へと進みながら、一つ奇妙なことに気づいた。
鍵がなくなってずっと放置されていた部屋にしては、家具や置物はほとんど埃を被ってはいなかった。どれもよく磨かれていて、むしろこまめに手入れされているように思えた。
私は入り口に面した壁に吊られている棚の上の置物にまず目をひかれた。木彫りの鳥、猫、熊などの動物。軽石を彫った小さな燈篭や橋。一つ一つ珍しげに眺めていく私の目にやがて一抱えほどの木製の綺麗な箱が映った。表面に蔦の絡まる模様が彫刻されているその箱に私は強く興味をひきつけられた。
そっと箱を持ち上げてみる。見かけよりはやや重たく、幼い私はしっかりと抱え上げた。
慎重に床の上に降ろす。上蓋は蝶番で斜めに開くようになっていて、正面を掛け金で留めてあった。私はためらいなく掛け金を外し、ゆっくりとその蓋を持ち上げた。
その途端、小さな、しかしはっきりとした金属音が一度だけ響いた。
私は一瞬身体をこわばらせたが、ほぼ同時にその音の正体に気づいていた。
箱はオルゴールだった。蓋を開けると、たくさんの小さな刺のある金属性の円筒とそれに平行して取り付けられている櫛形の金属板が目につく。どちらも綺麗な黄金色をしていて、薄暗い部屋の中でもほのかに輝いているように見えた。
隅にはゼンマイのねじがついていた。すでにゼンマイは切れているようで、蓋を開けたときのあの一音は残っていたわずかな復元力によるものらしかった。
私はねじを起こすと半回転ほど捻り、手を離した。
オルゴールは音楽を奏で始めた。軽やかな音色で、今までに聴いたことのない優しげなメロディが部屋の中を満たしていた。かすかにコーラスのような響き。遠くから聞こえてくるような鐘の音。
私はその音楽を耳にしたとたん、自分を見失ってしまったようだった。まるで雲の上に浮かんでいるような浮遊感を覚え、オルゴールの音に酔いしれていた。
気が付くと、いつのまにかオルゴールは鳴り止んでいて、私は床に伏して眠ってしまっていた。はっとして身体を起こすと、目の前にやや困ったような顔つきの祖父が立っていた。
「どうやってここへ入ったんだい?」
祖父の問いに、私は目を擦りながら鍵を見せた。
「そうか。これを見つけられてしまったか。いいかい、ここへは勝手に入ってはだめだよ。おじいさんの大事なものがいっぱいあるからね」
後になって知ったことだが、その部屋は亡くなった祖母の部屋だった。祖父にとってその部屋は祖母の思い出に浸れる特別な部屋だったのだろう。そこに飾られた調度品や思いでの品をむやみに荒されては困るという理由から、私たち子供をそこへ入れないようにしていたらしかった。
私は部屋から出そうとする祖父の手に逆らい、もう一度オルゴールを聴きたいと駄々をこねた。ところが、その祖父の返事は意外なものだった。
「オルゴール? ばかな。そのオルゴールはばあさんが亡くなるずっと以前に壊れているよ。夢でも見ていたんだろう」
祖父はそういいつつ、しかし、いいながらもしやと思ったのだろうか。私の手を離すと、オルゴールのゼンマイをキリキリと巻いた。
しかし、ゼンマイは空回りしているらしく、かすかにカタカタと音を立てるばかりで、先程聞いたあの音色は全く聞こえてはこなかった。
「ほらね」
祖父はそういいながら小さく嘆息し、オルゴールを棚に戻すとまた私の手を引いた。
私は呆然として棚の上のオルゴールを振り返ったまま祖父に引かれて部屋を出た。
その後、私はその部屋とオルゴールが忘れられず、祖父の家へ来るたびに中に入れてくれるようにせがんだ。しかし祖父はいつも逸らかして、子供の頃には再びその部屋に入ることは出来なかった。
やがて私は成人し、子供の頃のように頻繁に祖父の家を訪れることはなくなった。
そんなある日のこと。私はほんとうに久しぶりに祖父の家を訪れた。その気になればたいした時間を費やさずに来れる距離なのに、それは大人になるにつれだんだん遠くなる。
祖父は私の訪問を歓迎し、成人の祝いに何かプレゼントを贈りたいといった。私はしばし考えた後、あの部屋のオルゴールが欲しいと答えた。祖父は少しびっくりしたような顔をしたが、何もいわずに私を二階へ連れていくと、袂から取り出した鍵で、あかずの部屋の戸を開いた。
部屋は子供のときに見た時のまま変わっていなかった。ただ、私が記憶していたよりも部屋はずっと小さかった。
「このオルゴールのことか? お前がこの部屋に入った時にもいったと思うが、それは壊れているよ。それでもいいのか?」
私はうなずいた。そして、それを自分で直してみるつもりだといった。
祖父は快くそのオルゴールを私にプレゼントしてくれた。一言だけ付け加えて。
「もし、そのオルゴールが鳴るようになったら、おじいさんにも聞かせておくれ」
私はオルゴールを持ち帰るやいなやすぐに修理に取り掛かった。市販のキットのオルゴールや時計を組立てたことのある私は、小一時間のうちに歯車が一つ欠けていることが故障の原因であることをつきとめていた。幸い、持ち合わせの部品の中に使えそうな歯車を見つけ、それを取り付ける。さらに丹念に調べて他に故障箇所がないのを確認すると、私は気持ちを落ち着けてからゼンマイを巻いた。
ゼンマイの復元力がストッパーの外れた羽を目に見えない早さで回し、円筒がゆっくりと動き始める。
直った!
私は安堵の息を吐いた。そして、円筒の突起が発音体である櫛歯を弾くのを確かめながら、奏でられるメロディに耳を傾けた。
しかし・・・。
違う。私はオルゴールの調べを追いながら、心の中でつぶやいた。
子供の頃に聴いた音色とメロディ。それをはっきりと覚えているわけではない。しかし、もう一度耳にすればそれだとわかる自信はあった。ところが、今このオルゴールが奏でているのは、あの時のものとは違うように思える。
そのオルゴールに収録されている曲が全部で四曲あり、円筒部分を少しずらすことによって別の曲を演奏するということは、修理に取り掛かった時にすでに知っていた。だから、あの時のメロディがその内のどれであるかは実際に全部聴いてみなければわからない。にもかかわらず、いきなり最初の曲で「違う」と感じたのはメロディのせいではなく、その音色のせいだった。かすかに覚えているあの浮遊感を誘うような軽やかな音色、あの音色が再現されてはいなかった。
それでも私は収録されている四つの曲を聴き終るまで真剣に耳を傾け、自分の中にあるものと符合するところを探し求めた。しかし最後の曲が終わり、オルゴールのストッパーが掛かると、私は失意のため息をついた。
夢を見たんだろう。祖父はあの時そういった。私はそれが夢ではなかったと今日まで信じてきた。それとも・・・ほんとうに夢だったのだろうか。
次の週末、私は再び祖父の家を訪れた。約束通り、祖父に直ったオルゴールを聴かせてあげるためだ。
祖父は私を二階のあの部屋へと案内し、香りのよい紅茶を入れてくれた。私はオルゴールをもとあった棚に置き、紅茶をすすりながら静かに蓋を開けた。
祖父は木の椅子に腰掛け、目を閉じてじっと聴いていた。
同じ曲を二回ずつ四曲総ての演奏が終わり、オルゴールが自動的に止まると、祖父は目を開いて私の方を向き、よく直したものだと誉めてくれた。
しかし、私は愛想笑いをしただけで、再び耳にするオルゴールの音色にため息をついていた。
「どうした? こんなに早く、これほどきちんと直したにしては浮かない顔じゃないか」
その問いに私は瞹昧な返事を返したが、私の言葉を待って黙っている祖父に思い切って自分の考えていることを話してみることにした。
祖父は、私の話を何度もうなずきながら聞いていた。
そうして私が話し終わると、ゆっくりとした口調で話し始めた。
「このオルゴールを聴きながら、昔ばあさんがいっていたことを思い出したよ。まだこのオルゴールが壊れていない時に、二人で聴きながら、ばあさんがこんなことをいっていた。ずっと昔、このオルゴールを聴き始めたころ、オルゴールに夢を見せて貰ったことがある、と。当時、私は何の事だか分からず笑って聞いていたがね」
私は祖父の言葉に何か自分の中の疑問の答えを得たような気がした。
あれはオルゴールが見せてくれた夢。そうかもしれない。まだ夢と現実の狭間を掴みきれていない子供にオルゴールが聞かせてくれた夢だったのかもしれない。
昼下がりの日が通風口から差し込む薄暗い部屋で、私は幼い頃の自分に思いを馳せながら静かにオルゴールの蓋を閉じた。
(了)