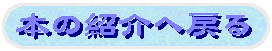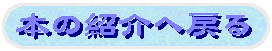
|
*1 シリンダー・オルゴール 金属製の円筒(シリンダー)に短いピンを打ち込み、この円筒をゼンマイ等で回転させ、ピンが直接調律された櫛状の金属板を弾くことによって音楽を奏でるオルゴール。一曲の演奏時間が短いことや簡単にシリンダーを交換できないため、複数の曲を演奏することが困難であるといった欠点をもつ。一本のシリンダーに複数の曲を収録したものや、シリンダー交換型のものも作られたが、やがてディスク・オルゴールへと移り変わっていった。 現在、ファンシーショップなどで見かけるオルゴールのほとんどはこのシリンダー・オルゴールの簡易版である。
*2 ディスク・オルゴール
*3 ホール・オブ・ホールズ
*4 ストリート・オルガン
*5 オート・マタ
*6 自動演奏ピアノ
*7 コンピューター・ミュージック
*8 カセットタイプオルゴール *9 これは実際に手回しのオルゴールを机の上に置いて回してみるとよくわかる。けっこう大きな音になる。
*10 普通のストリート・オルガンのハンドルは片手で難なく回せるくらいの大きさだが、中には蒸気機関車の車輪ほど大きいものもある。先に紹介した「ホール・オブ・ホールズ」にこれに当るものが展示されていて、コンサートの時に実際に回させてくれる。
*11 ICカード
*12 ボトルブロー
*13 オーケストリオン
*14 ジュークボックス
|
オルゴールと聞いて思い浮かべるものはどんなものだろうか。 多くのひとは宝石箱のオルゴールや、最近ファンシーショップなどでよく見かける手回しの小さなオルゴールを思い出すのではないだろうか。しゃれた喫茶店やアンティークの店におかれているシリンダー・オルゴール(※1)やディスク・オルゴール(※2)を思い出す人もいるかもしれない。この本を読んでいるあなたは「ホール・オブ・ホールズ(※3)」の様々なオルゴール、ストリート・オルガン(※4)やオート・マタ(自動人形)(※5)、自動演奏ピアノ(※6)などを思い浮かべたかもしれない。 オルゴールとは、もちろん特定の形状をしたもののみをさして呼ばれている言葉ではない。自動演奏装置(Mechanical Musical Instruments)のことである。 日本オルゴール協会の定義によると「オルゴールとは、手動または自動的に音楽を演奏する機械で、櫛歯に似た特殊鋼製の発音体(鳴金または振動板)を回転胴(ドラム)に植えつけられているピンで弾き、自動的にメロディを奏でるもの」となっている。しかし、この定義はかなり狭義だと思う。これではストリート・オルガンや自動ピアノは音を指定する部分にも音を鳴らす部分にもあてはまらない。他にも弦を発音体としたオルゴールや、ディスク・オルゴールでさえ正確にはあてはまらない。 大雑把な定義になるが、「音楽を自動演奏させる機械の総称」とすればこれら総てを含むことができる。 しかし、この定義も正しい表現とはいいきれない。 そのよい例がコンピューター・ミュージック(※7)。これは現在のところ最も極めた形の自動演奏装置の姿であろう。正確なリズム、音階、そして多彩な音色。しかしこれをオルゴールと呼ぶ人はまずいないだろう。 それでは、どういったものをオルゴールと呼び、どんなものがオルゴールと呼ぶにふさわしくないのだろうか。それについて独断と偏見を交えて考察してみようというのが、本文のテーマである。
今日さまざまなオルゴールが存在する。
* * *
十九世紀から二十世紀前半に全盛期を迎えたオルゴールの製造技術は、現在ほとんど失われているという。今日作られているオルゴールはその頃の技術の一部を復活して製作されているにすぎない。まだ、いろいろな発展の可能性のあったオルゴールが、蓄音機やラジオに一掃されていったことは、やむを得ないだろうと思う半面、残念でならない。
◇櫛歯の二枚付いた輪唱オルゴール
◇シリンダーに平行移動機能のついたオルゴール
*15 歓喜の歌 | もちろん、ベートーヴェン作曲交響曲第九番「合唱付」の中の第四楽章で歌われるシラー作「歓喜に寄す」のことである。 関係ないが、年末になるとこの第九が演奏されるが、あれは日本独自のものらしい。
◇複数のシリンダーと櫛歯を持つ合唱できるオルゴール | 同じ音でも同時に鳴らせば厚みができる。まったく同じものを鳴らしてもいいし、高音部と低音部に分けてもいい。その気があれば四部構成で「歓喜の歌(※15)」を鳴らすのもいいかもしれない。しかし、分割するのであれば一つのシリンダーと櫛歯でもアレンジによっては可能だ。そう考えると二つの手回しオルゴールを同時に回せるようなオルゴール台でも作ったほうが効率がいいだろう。
◇発音体を選択できる打楽器向けオルゴール
◇風車を動力としたオルゴール
*16 巨人の星 | 知らない人はまずいないと思うがかつて「スポコン」という言葉を流行らせるきっかけを作った野球マンガである。 「スポコン」という言葉は死語になったが、いまだにギャグのネタに使われることがある。
◇学校向けローラータイプオルゴール | これは全くの冗談である。テニスコートなどをならす重いローラーの中にオルゴールを仕込み、ローラーを引くと音楽が鳴るというものだ。野球部の体力作りに「巨人の星(※16)」なんかいいかもいれない。 以上が私の偏見に満ちたオルゴールに関する考察である。実はオルゴールについてはちょっとかじった程度にしか知識がなく、とても真正面から考察したものが書けないため、このような内容で書くことになってしまった。本当にオルゴールを愛している人には申し訳ないことを書いてしまったと思うが、どうか笑って勘弁していただきたい。 (この場を借りまして、私にオルゴールの本当の良さを教えてくれた「ホール・オブ・ホールズ」の皆さんに、深く御礼申し上げます) 参考文献:音楽之友社刊 名村義人著「オルゴールの詩」
|
注意:注釈※3の「ホール・オブ・ホールズ」についての記述の中で、オルゴールコンサートのことが書かれていますが、現在は水曜日と土曜日に変更になっています。
また、本文中のストリートオルガンの動力に関する記述で、「人力が普通」とありますが、これは間違いで、蒸気モーターなどが使われていました。「ホール・オブ・ホールズ」で、最初の頃はよく人力で廻していたため、そういうものなのかと勘違いしてしまったのです。